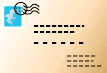
平成18年1月16日 菅原 登 様 植田 裕 2つの資料をお送りします。1つは、資料Aで、最近、書類を整理していて出てきま した。 1枚めの「第8回全中大会優勝者 大阪天商 作田武一君速記原文」の下線に注目し てください。普通であれば途中で区切って書くところです。それを続けて書いています。 この書法が、現在の私の“書風”の原点になっています。例えば2枚目の*印の下線部 分「大きな節目の年である」という書き方であります。 また、単に連続して書くというだけでなく、同じページの2本線の部分「世界大戦が 終わりまして」(大戦=ポジション記法、旧名・特殊漢音縮記法は、終わり=ア・オ列 表示記法)、「高度成長の時代」(成長、時代=ポジション記法)のように、本来は2 単群になるところを1単群にまとめる記法の開発につながっていきます。 さらに、「迎えました」の「迎え」のように、中部加点によるスミニヒカリシのカの 加点を、ウスヌムル音をあらわす正側頭部に移行して、ムとカをSM(サインマルチ) 記法であらわし、その加点を前符号の尾部にひそませる、つまり、前符号を利用しなが ら後符号を書く方法に発展していくわけです。 同じことは、7枚めの下線の部分、「奥邨 (オクムラ)宗務総長におかれましては」の場合、オクムラは、ラの正側頭部に加点で すが、その加点は、オクのオの符号の尾部に(ク符号は逆記されるので)ひそまれます。 シュウというのも同じく正側頭部加点ですから、「総長」のソウの符号の正側頭部に加 点して、シュウとムを同時にあらわすSM記法で書きますが、そのシュウとムの加点は、 オクムラのラの尾部にひそませます。 「さぬきうどん」の場合、「キ」の正側頭部加点で「ヌキ」となり、「サ」の尾部に、 その加点をひそませて「サヌキ」 次に、「ド」の正側頭部に加点して「ウド」 この負側頭部の加点を、さきの「サヌキ」の「キ」の尾部にひそませると、 「宗務院」というのは、「シュウ」も「ム」も正側頭部に加点してあらわします。た またま「シュウ」と「ム」が続いたわけですが、SM記法で「イ」の正側頭部に点を1 つだけ打って「シュウム・イ」 「日蓮宗」は「ニチ」の最大線であらわします。その尾部に こうした方法で、「さぬきうどん」は さて、資料Aは、検定試験問題を符号化したのは別にして、平成8年ないし9年に私 が現場で速記した原文帳からのコピーです。 実は、これを教材にして、衆議院のS.Sさん、Y.Iさんに、私の“書風”を伝授し ようとしたわけです。しかし、既に大成して衆議院の速記者になっているお2人に、今 さら符号の形を変えて書けなんて、非常におこがましいことなので、そのことは断念し て、略符号並びに縮記法を応用して簡単に略符号的に書けるもの、いわゆる「簡字」を 50音順に約2年間かけて、中根速記学校で教えました。(この講習の初期には、石巻の T.Mさんも参加していました。) 今まで私の符号として出ているものは、生の符号ではなく、文章を見ながら符号化し たものです。その点、資料Aは、先ほど述べたように、検定問題を符号化したもの以外 は、講演、インタビュー、労組大会、日蓮宗宗会など、すべて現場で速記した生の符号 です。したがって、文章を見ながら符号化したものとは迫力は違うと思います。 同封書類の2つめ資料B「気になる速記文字」は昨年の東京速記士会下期研修会で発 表したものです。(一部、説明の冗長な部分は改訂しました。)学生時代に出会った専 門家の書いた「潜水艦」という符号にこだわり続け、現在では そこで、唐突で申しわけありませんが、資料A、Bを『速記道楽』で全国に紹介して いただければと思っておりますが、いかがでしょうか。
ところで、私が日ごろから新しい書き方をメモしているのは御承知だと思いますが、
私も年老いて、いつあの世へ行くかわかりませんので、新しい書き方を思いつく都度、
そちらに報告しますので、『速記道楽』で取り上げていただければ幸いです。 |