| �� 2005/04/17 (�run)�@�����Љ�@���������L�@�u�K�� |
�@�X�@�얾���u���㍑��\�ۑ��L�@�v�i���s���L�������@���a52�N�U���P�����s�j�Ɂu��
�������L�@�u�K��v�\�\50�N�̘̂b�\�\���f�ڂ���Ă���܂��B
�@
�@�吳�W�N�̏t����A�����̑��̏��w�Z�̋��t�����Ă������́A���̉ċ��s�֗����B���������㋞�����̂ł��邩��A���̑؍݊��Ԃ�L���Ɏg�������Ǝv���āA�����A�����ق�}���فA�������Ղ́A�܂����Ă��Ȃ��Ƃ�����ςĉ�����B���ƈ���āA���̂���́A�u�K����u������قƂ�ǂȂ������B
�@�Ƃ��낪�A�}���ق���o�āA���R�ʂ���F��̕��֕������\�\�����͓��R�����A�F���
������ۑ����Ȃ����Ă����B�d�Ԃ�҂ԂӂƓd����������A���̂悤�ȃR���j���N�ł̍L���������Ă������B
�@
�@�@�@��l�� ���������L�@�u�K��
�@��@�Á@�F���s���L�w�Z
�@���@���@������������Z���ԁ@���鎵��������
�@�@�@�@�@�A�@�����ڂ͒��u����
�@��@��@�O���@�N���
�@��@��@��~�E�K�@�A����Ɠ����ɔ[�t�̂���
�@�@�@�@�@�i���Ӂ@�\���͖��h��p�ɂč��x�Ȃ�����̓y���ƃm�[�g���Q���肽���j
�@�{���L�@�́A�吳�O�N�܌��@��㖈���V���Ɉ˂菉�߂č]�ɏЉ���A�����ՊȖ��A�a�V�Ƒn�I�Ȃ�́A�z�E��y�����ċ��|�����ߊ��V������L���A�ŋߔV�����y�̈�[���L���A������l�\�Z�������Z�c�S�l�\���u�K�A�����ۊC�R�y�э����ێs��Íu�K��S���A�W�s�������u�K�ɉ��͂�A���C�R�����ؑ������̊��ӏ����̂��B�X�ɒ���s�ɂĂ͖{�N�܌����荂�����Ɗw�Z�A�W��w���w�Z�A�������蒆�w�Z�A���q�Z�A���Ɗw�Z�ɉ����Ė{���L�u�K����J�Â��A���������ҌܕS�����Z���B���O�����s��ꏤ�Ɗw�Z�ɉ����ē��l�u�����тɎ��Z���s�Ј�疼�̊w���ɑ���̊�����^�ցA���ɑ�Ɗw�Z�ɉ����Ă͍u�K���J�Â��W�Z�����V�i�s���j�������u����ꂽ��B
�i�����̂܂܁j
�@���L�Ƃ������O�́A�̍������w�Z�̂P�N���i�����P�j�̂Ƃ��A���搶�i�� ���ш��c�m�j����A���������ŗL���ȓ��c�O�Y�̘b�̂Ƃ������Ēm���Ă��������A���̉Ď��̊w�Z�ŐN�c�̍u�K�������𖽂����č���������ł������̂ŁA���L�ł��K���ċA�낤�Ǝv���������̂ł���B
�@�O��ʂ��G�ےʂ肩�瓌�֖��n��܂ł����ƁA����N��قƂ����ؑ��O�K���Ă̗m
�فi�����F���a52�N�U�����݁j���������B�����͂܂��͌����ʂ�ɓd�Ԃ͂Ȃ������B
���͓c�ɂ̋����u�K��̂悤�ɁA���S���̎�u�������邱�Ƃ�\�z���Ă����Ă݂�ƁA��K�̈ꎺ�̑O�̘L���Ɏ�t�������āA�Ⴂ�j���̂Q�l���o�Ȏ҂J�Ɍ}���Ă����B
�@���ɂ͊���20�l����̐l���W�܂��ĊJ�u��҂��Ă���B���̍��[�ɂ͎��̂悤�ȕ\�������Ă���B
�i��50���\�͏ȗ��j
�@
�@���̃v�����g�́A�����z��ꂽ�̂ł���B�������搶���瑬�L�̘b�����Ƃ��A���L�Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂��낤�A�� �j�̂悤�Ȑ��ŏ����̂ł͂Ȃ����낤���A�Ƒz�����Ă݂����Ƃ����邪�A����50���\�������Ƃ���ɁA�����A����ς肠�����������A�Ə��߂Č��鎚�̂悤�Ɏv���Ȃ������B
�@�₪�ču�t�́A�����Ғ������e�搶�����ߎp�ł����ꂽ�B�����̃I�[���o�b�N�A�w��̍����A��̑傫�ȁA�z�̍L���A����Ă��ĈĊO�ׂ��_�o���Ȑ��ŁA�ʂɏЉ���҂����ɐ������n�߂�ꂽ�B���̂���̐搶���݂Ȃ���Ă����悤�ɍׂ��|�̃��`��U��Ȃ���
�g���L�@�Ƃ������̂̓l�h�ƌ�����
�@�@�@����h�@�@�c���@�@�F��
�@�@�@�ܒ��h�@�@�K���g���b�g
�@�@�@�P��h�@�@���c�@�@����
�Ə����Ă��̂P�P�ɂ��āA�|�c���|�c���Ƃ��Ⴍ�����悤�Ȑ��ŌЋC�̂Ȃ����߂̂܂����Ă������Ă��鑳�����ɏグ�グ���������̂ł���B
�u�䂪���̑��L�E�͂܂��c�����������A�Ⴆ�g���Ɂh�́A�@�@ �Ə����A�{�N�̎��ł́@�@�@�ł悢�B�v
�ƕ����āA�Ȃ�قǒ������͐i�����ȁA�Ɗ��S�����B
�u�{�N�̓l�A����̋�w������������A�p��̑��L����K���Ă���l�̂Ƃ���ɘN�ǂɍs���Ċw���̑����ɂ��Ă����B���̂Ƃ����߂đ��L��m�����B���ꂩ����{��̑��L�@���K�������Ǝv���āA������Ԑi��ł���Ǝv����F�蔎�m�i���͔��m�ł͂Ȃ��������Ă�������ꂽ�j�̔����ɂ�����F�莮���������ė��K�ɂ��������B���Ȃ��Ȃ����x���o�Ȃ��B����ʼn��߂āA���Č��Ă����p��̃s�b�g�}�����̌������n�߂��B�܂����̒Ԏ��`�̔������̂ɖ�����ꂽ�B�c�������s�b�g�}��������{���ɓ��Ă��搶�͓����������`���R���b�ƕς���Ă���B����͉p��̃A���t�@�x�b�g����{��̃J�i�ɒ������炾�ƋC�����āA����ɂ͓��{��ɑ������ɁA�p��ɑ������̐��Ă���悢�A�ƍl���āA�������������݂�������ƐV����50���\�����邱�Ƃ��ł����B������]���̕��掮��ܒ����ƈ���āA���c���̂悤�ȒP�掮�ɂ����̂��v
�Ƃ����悤�ɁA���������Ă̓��@����A���̌����̈�ʂ��q�ׂču�`�͏I������B�f����ꂽ50���\�̐����͂Ƃ��Ƃ��ꌾ���Ȃ��������A���͏h�ɋA���āA���̔ӂ̂�����50�������S�Ɋo���邱�Ƃ��ł����̂ł���B�@
�@
�@
���̑��L�����̕����Łg���Ɂh�́A�������Ő�������Ɓ@�_ �̖����ɑȉ~�k���l�A�\ �̖����ɏ��~�k�����̃n�𐳑��l�ɂ��ĘA�Ԃ����`�ł����A�F�莮�̃^�s�� �^�ł����A�c�����̃^�s�� �b �ł��B�V�c�����ł��ȉ~�̕������Ⴂ�܂��B�k�����j�̌`�l
�@
���c�����A�V�c�����A�F�莮�̊�{�����ɂ��Ắk���L��{���������l���Q�Ƃ��Ă��������B
�@
���u�{�N�̕����ł́v�Ɛ������ꂽ�g���Ɂh�̑��L������ �_ �g�̑��L�����̃N�́A�p�J�M�ł͂Ȃ����J�M�𐳑������ɂ��Ă���܂����A�����̃j�́A���J�M�������ɂ��Ă���܂��B
�@
�@
| �� 2005/04/14 (�shu)�@���L�����ٕ��u��{���ɂ��ĂT�v |
�@���L�����فu�������̏Љ�ƕ]���v�Œ��������搶�́g��{���ɂ��ĂP�`�S�h���f�ڂ��Ă���܂����A�u��{���ɂ��ĂT�v�i�������L����@�֎��u���L�v���a�V�N12���� �mo.29�j�̕������o�Ă��܂����̂ŁA�u���L�����ٕ��v�Ƃ��ďЉ�����܂��B
����{�����͌f�ڂ������܂���B�@
�@
�@��{���ɂ��āi�T�j
��������
�@��{���ɂ��Ă͂��͂�O���܂łő�̗�������ꂽ�Ǝv���̂ŁA���͑O���őł��邱�Ƃɂ��Ă����̂ł��邪�A�O�̂��ߏ�����50���}���f���Đ������������邱�Ƃɂ��Ă����܂��B
�@�܂������ɂ����Ă͂����Ɏ����Ă���Ƃ���A�A�s�̕�����45�x�ł����āA�����������E��ɏ����グ�Ă����̂����݂�30�x�̐��ɂ��č�����E��ɏ����グ�邱�Ƃɂ��Ă���܂��B�T�s��������45�x�̐��ł��������A��������݂�30�x�̐��ɂ��Ă���܂��B�^�s�̒��A�^�ƃg�͏�����60�x�̐��ł������̂����݂�30�x�̐��ɂ��Ă���܂��B���ꂩ�烄�s�A���s�A���s�Ȃǂ͏����ɂ����Ă͂���������̐}�̂Ƃ���45�x�ɂȂ��Ă��āA������ォ�獶���ɏ������낵�Ă����̂����݂ł͂������60�x�ɋN�����āA�ォ�獶���ɏ������낷�悤�ɂ����̂ł���܂��B
�@�������Ă���ɂ���Ă킩��Ƃ���A�����ɂ����ăA�ƃ��A�C�ƃ��A�E�ƃ��A�G�ƃ��A�I�ƃ��͂��ꂼ��45�x�̓��`�����ł������̂łP�̐������𗣂��ď�������ǂ���ɓǂނ��킩��Ȃ������̂ł���܂��B�]���Đ��O��̕��͂ɂ���Ĕ��ǂ���悤�ɂ��Ă����̂ł���܂��B���������������̓A�s�͍�����E��ɏ����グ�A���s�ƃ��s�͓����`�̕����ł��������A�E���獶���ɏ������낵�Ă����̂ŁA�������̕����ƘA�����ď����ꍇ�͂������A��ڂ��ĉ��̎��Ƃ������Ƃ��������邱�Ƃ��ł����̂ł���܂��B����������͌��݂ɂ����Ă̓A�s��30�x�ɁA���s�A���s��60�x�ɕς��A�X�̓x���Ⴄ���ƂɂȂ�A�P���Ƃ��ē����`�̕����͂Ȃ��悤�ɂȂ�A�]���Ăǂ��ɂ����Ă��A���Ƃ��P����������Ă����Ă��A�͂����艽�̎��ł���Ƃ������Ƃ̌����������悤�ɂȂ�A���������̕��@�������I���Ƃ������ƂɂȂ����̂ł���܂��B
�@�ȏ㐔��ɂ킽������ɂ���ĉ��䂦�ɏ�����50���}�ɕύX�����������ɂ��Ă͏\���ɗ�������ꂽ���ƂƎv���܂������{���ɂ��Ă͂���őł���A����Ɉ���������\���邱�Ƃɂ��܂��B�i�I�j
�@
�������Ƃ����̂́A�������e�搶���n�Ă��ꂽ�̌n�̂��Ƃł����A�������̊�{���́i�b�j�i���j�i���j������܂����B
�@�i�b�j�� �_ �^�A�g�i60�x�j�A�\ �J�A�R�i�O�x�j�A�^�i�ォ�獶���j�L�A�P�i60�x�j�A �^�i������E��j�c�A�t�i30�x�j�A�b�N�A�`�A�e�i90�x�j�̒����ɑ��Ďg�p����Ă���܂����B
�@�i���j�́���×�Ő�S�������ă}�s�A�i�s�A�n�A�q�A�w�A�z�̋Ȑ��Ɏg�p���Ă���܂��B
�@�i���j�́����{�Ő�S�������ăA�s�A���s�A�T�s��45�x�̋Ȑ��Ɏg�p���Ă���܂��B
�@������ �_ ��60�x�ł��B�T�s�́_ �p�x�́����S���������`�ł�����45�x�ɂȂ�܂��B
�@���������搶�ɂ���āA�����S������������o���}��p�~���āA���݂�30�x�P�ʂ���{���̊p�x�ɂȂ��Ă���܂��B
�@
�@
| �� 2005/04/04 (�lon)�@�����Љ�@�䂪���̌ւ�ȗ��@ |
�@�������L����@�֎��u���L����v���a32�N�W�����ɒr�c����搶�́u�䂪���̌ւ�ȗ��@�v���f�ڂ���Ă���܂��B
�@���{���L����@�֎��u���{�̑��L�v���a32�N�U�����Ɍf�ڂ��ꂽ���e��]�ڂ��ꂽ���̂ł��B
�@�u���L�G���v�ɂ͐}�ł��f�ڂł��܂���̂ŁA�u���L�@���̕����v�g�������L�w�Z�̑̌n�h�����Q�Ƃ��������B
�@
�䂪���̌ւ�ȗ��@
�@
�P�D�T��
�@���������L�@�́A�����s���m�w�����������e�搶����݊w���ɂ������S�̑n�ĂɂȂ���̂ŁA�吳�R�N�T��10����㖈���V���ɂ���ď��߂Đ��ɏЉ�ꂽ���̂ł���B�����ߒ퐳���搶�听�A���{�S���͂��Ƃ�蒩�N�A��p�A���B�ɂ܂ŕ��y�����č����Ɏ��������̂ł���B
�@�������̎�Ȃ�����Ƃ���Ƃ����
�@�P�D���Ă̍��{���ɂ߂ĉȊw�I�ł���
�@�Q�D�Ƒn�I�Ȗ@���ɂ���č\������Ă���
�@�R�D�@�����Ȗ��ł��̌��ʑ�Ȃ�_
�@�S�D���{�@���ɕύX�̗]�n�Ȃ��ǐS�I�n��
�@�T�D�Ȋw�I�Ȗ@�����������ɔ��W�I�ɓW�J�ł���
���ƂȂǂł���B
�@���悻���L�@�ɂ͑S�ĉ��^�n�ĉ��X���Ȃ閼�̂��������Ă��邪�A�����ĉ��^�n�ĉ��X���Ȃ閼�̂�������ȏ�A���̕����̓��e�ɂ����āA�����ɂ��̖��̂������Ă͂���Ȃ������̓Ǝ������Ȃ���Ȃ��͂��ł���B�����������L�@�̖@����䂦��w�I���l�Ƃ������̂́u�{��𗝘_�I�ɒZ�k����A���̖@���v�ɂ���̂ł����āA��ɒʂ��ē�ɒʂ��Ȃ������̂��Ƃ��A�܂��P�Ȃ�50���̉��ςȂǂ̂��Ƃ��͉��l�̂Ȃ����̂Ƃ��Ă悩�낤�B������ɁA�ŋߑ��L�E�̎����ɏ���ĉ��X���L�����Ƃ����ɂ͐r���������킵�����̂��ǐS�I�Ȃ���̂����^�n�ĉ��X���̖��̂������āA�k�Ɍ֑�Ȑ�`�������܂������āA��ʐ��l����킵���邱�Ƃ́A�z�E�̐���Ȕ��W��j�Q������̂ɂ��āA�܂��ƂɈ⊶�ł���B
�@������A���̌��������̓Ǝ������������L�@�̒���������䂦��̂��̂͂ǂ���
����̂��ƌ����@�@���Ă̍��{���j�Ɓ@�A�������̓S���i��q�j�����ɔ�����A�̓Ƒn�I�u�@���v�ɂ���Ƃ������Ƃ��ł���B�ȉ���̓I�ɏq�ׂĂ݂悤�B
�@
�Q�D���Ă̍��{���j
�@���������L�@���Ă̍��{���Ȃ����̂́u���{��͊����Ɖ����ł���킳��邩��A���̗������ł��ȒP�ɂ��Ȃ���ΗD�ꂽ���L�@�͂ł��Ȃ��v�Ƃ����̂����̍��q�ł���B�����āA�u���͂��犿���̕����������A�����̕����Ƃ��Ďc��̂͏����̏����A�������A�`�e���̌���v���炢�̂��̂ł���B�]���Ă܂����̑����̊����̏����̉�������łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������O�Ɋ�Â��ė��Ă̕��j�����肳�ꂽ�B
�@�����ʼn��P��l�܂��Ƃɕ��G����܂�Ȃ����̑����̊��������̂��߂̋����ɑ�Ȃ�w�͂������A��S�̌��ʁA���ɂQ������Ȃ銿���̔����́u�C���c�`�N�L�v�Ȃ�Ƃ������S���̔����ƂȂ�A���̉���Z�k������@�Ƃ��āA�t�L�ɂ��u�C���c�N�L�@�v�̑n��������Ɏ������̂ł���B�����ŁA�����̌P�ǂ݂̏ꍇ�̏������@�Ƃ��Ă͌P�Ǔ]���@��߉��@���l�Ă���A�Ō�������̕����̏������@�Ƃ��ē��Ɋ����Ɖ����̕����Ƃ̘A�ԉ^�p�̖��������邽�߂ɂ��P��łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������_�̂��Ƃ�50���̂P���P�����z�肳�ꂽ�B����ɑ����āA���������痈�钷�X���̓E���̋t�L�̌`���Ƃ�A�����A�����A�ő���A���_�������@���X�a�V�Ȃ�A�C�f�A�ɂ���āA���̌��p�ɂ߂đ�Ȃ鍪�{�@�����ďo���ꂽ�̂ł���B
�@�������n�Ĕ��\�����A�ݗ��̕����͂����ނˁu���t�͉��Ɖ��Ƃ̘A���ł���v�Ƃ������O����A�܂�50�����Ɍ��肵�A�@���炵�����̂́u���s�k���v���炢�̂��̂őS�Ă𗪎��ɗ��炴��Ȃ������̂ɑ��A�����������t������킷�����̉Ȋw�I�����Ɏn�܂�A�����̐��i�𖾂炩�ɂ��āA�܂��@�����l�����A���_�I�{��Z�k�ɕK�v�Ȃ�50���̔z������̌�Ɍ��������Ƃ����Ƃ���ɁA���������ݗ��̂��̂Ƃ��̗��Ă̍��{���j���قɂ��Ă�����̂ł����āA�����\���̑�@���������܂ł��Ȋw�I�Ƒn�I�Ȃ�Ƃ���ɁA���̌����{���̓Ǝ���������A�]���đn�Ă̖��̂������Ă͂���Ȃ����������L�@�̒���������䂦��̑�����Ƃ���ł���B
�@
�R�D�@��
�k��P�}�l
����{�����\�͏ȗ�
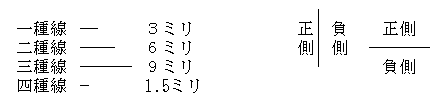
�P�j��{�����̍\��
�@50���̊�{�����͑�P�}�̂��Ƃ�
�@�A���Q���I��@�@�C���Q���G��
�@�A��̔��܂��͔Z�����ăC��
�@�E��̓I��{�_�@�@�N�c�t���͗�O
�ƂȂ��Ă��邪�A��{���Ɏ����ꂽ�T�����̒��Z�i�����y�ѓ����j�Ȓ��A�Z�W�A���_�ɂ���č\������Ă���B���̓����Ƃ���Ƃ���͕ꉹ���q�������i�̐���z�����ĘA�Ԃ̍ۃC���c�i�`�j�N�L�������t�L���A����ɖ����͏��������ɂ���ďk������ɕւȂ炵�߂��Ƃ���ł���B�{���ŕ����Ƃ����̂͑�~�A���~�A�ȉ~�A��J�M�A���J�M���̂��Ƃł���B
�@
�Q�j�����y�є�����
�@�����͔Z���������Ă���킵�A�O�u�d�͐��������ɉ��_�Ƃ���B�������͐����ɏ����~������B
�@
�R�j���X��
�@��P�}��{�����A��A�C��A�E��A�G��A�I��e��̕����̓����ɒ����͐����A�Ȑ��͓����ɑ�J�M�����Ē����y�ѝX��������킷�B�E��y�уI��͕��ʂ̒����ɓǂ݁A�C��y�уG��͝X�����A�A��͝X�Z���ɓǂނ̂ł���B
�k���l��O�u�^�v�u�g�v�̕����ɑ�J�M�����āu�V���v�u�V���v�Ɠǂ݁u�f�v�̐����ɂ��āu�����v�ƓǂށB���̑��X�Z���������Ɠ��`�ɂȂ�ꍇ�A�����͕����A�Ȑ��͑�J�M�ɓ��ɉ��_����B
�@
�S�j�C���c�N�L�@
�@�����̂����A�Q������Ȃ���̂͋t�L�@�ŏ����̂��C���c�N�L�@�ł���B���̋t�L�@�Ƃ����̂͗Ⴆ�`���{�a���ƂȂ��Ă���Ƃ��A�a�����ł���킵�`������{�����ŏ����t�L�A�܂�J�C�Ə����̂ɃJ�̊�{�����̓��ɃC�̕����������Ă����Ƃ����������ł���B���̋t�L�@�����͒������̈������Ƃ���Ƃ���̑S���Ƒn�I�Ȃ�k���@�̂P�ł����B�Ȃ��A����͊������݂̂Ɍ��炸�C���c�i�`�j�N�L�̉��Ȃ������ꍇ�Ɋ��p���č����x���Ȃ��B
�k�C�̏������l���鉹�̎��ɃC�̉�������Ƃ��́A���̂��鉹�̓����ɑ�~������B��R�����邢�͂���ȉ��̏ꍇ�����l�ł���B
�k���l�����͐����A�Ȑ��͓����i�ȉ������j
�k���̏������l���������Ă��鉹�͑S�ē����ɏ��~������B
�k�c�̏������l�ʏ�c�̉����Q���ڂɗ���Ƃ��͓����ɏ��ȉ~�A��R���ڈȉ��ɗ���ꍇ�͋�ԂƂ���B�Ȃ��A�l���̏������͑O���̖����ƌ㎚�̓������������A�������̒����͕��s����悤�ɏ����B
�k�`�̏������l�Q���ڂɗ���`�̉��͌��я��~�Ƃ��A�R���ڈȉ��ɗ���ꍇ�̓��̏��~�������O���ɉ��_����B
�k�N�̏������l�Q���ڂ̃N�̉��͊p�J�M�Ƃ��A�R�����Ƃ͊p�o�J�M�ɏ����B
�k�L�̏������l�L�̉��̓`�̏������Ɠ��l�ŁA�`�̏ꍇ�̏��~���L�����ё�~�Ƃ��A�R���ڈȉ��͑�~�����_�܂��͋l���̏������̂悤�Ɍ�������B
�k���l�X�Z���ƃN�Ȃǂ̏ڍׂ͒����Q�l����ꂽ���B
�@
�T�j����
�@�����̏����n�߂����p����u�C���c�N�L�@�v�ɑ��A�����I�������p���ďk������̂��{���̏����̏������ł���B
�@
�U�j�㉺�i�@
�@���S���̏㉺�̈ʒu�����p����̂ŁA�㉺�i�@�Ƃ������A��i�ɂ͌P�Ǔ]���@�ɂ���Ċ����̌P�ǂ����L���A�̒d�ɂ͓����A�������𗪋L����B
�@��i�̌P�Ǔ]���@�Ƃ����̂͗Ⴆ���^�N�V�\���\�V�A�J�G���~���\�ځ\�R�A�E�P�^�}�����\���\�V���E�i�Z�E�j�Ȃǂ̂悤�ɂP������Ȃ銿���̌P�ǂ݂������ŏ�i�ɏ����A�����̍ہA�P�ǂ݂��邷����@�ł���B����͕��ʂ̗���͂�L����҂Ȃ瓯���̂��̂����p���Ă����ӕ����ɂ���Ĕ��ǂł��A�����Ԃ�Z�ʉ��p�̂����k���@�ł���ƌ�����B���i�ɂ̓R���A�J���A�����A�i���A�^���Ȃǂ̃��s�ȗ��y�уA���A�I���A�C���A�X���A�i�P���o�i�����Ȃǂɂ��悻30���̊�{���������̓ǂݕ��Ɋ��p����B
�@
�V�j�߉��@
�@�P�ǂ݂̌��t�łR�ȏ�̐߉�����Ȃ���̂�߉���Ƃ������A���̂Q�̐߉������ԂƂ��A���Ԃɏ��J�M��p���ďk������B�Ⴆ���K�N�j�̏ꍇ�A���ƃN�̊�{�����̒��Ԃɏ��J�M�����ď������@�ŁA�܂����ԏ��J�M�@�Ƃ������B����܂����p���݂Ŋ��p�͍L���B
�@
�W)�ő��
�@��{�������O����Ɋ��p���ďȗ�������@���ő���Ə̂��A����Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA���t�̒��ɂ͏��߂̂P�����͂����肵�Ă���Ύ��̎��́��ł����ӕ����ɂ���ĊԈႢ�Ȃ����m�ɔ��ǂł�����̂��������邪�A�����������ǂɍ����x���Ȃ����t�̍ŏ��̂P�������܂�ő���ɂ��āA��̎��͏ȗ�����̂ł���B���̍ő���̊��p�͐߉��@�Ɠ��l�A���̌��ʑ�Ȃ�ȗ��@�Ƃ������Ƃ��ł���B
�@
�X�j���_�@
�@���L�������̂��̂̈ʒu�ɉ��_���A����Ȃ�ȗ����Ȃ��B����̕ω��͉��_�̈ʒu�ɑ�l����i�ŏ����j�����p����B
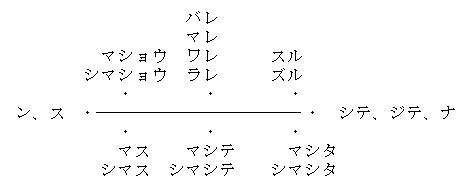
10�j���_�C���c�N�L�@
�@�S������Ȃ鉹�Ǐn����ʒu�ƕ����ɂ���ďȗ�������@�ŁA��P���͊�{�����ŏ����A��Q���ڂ͈ʒu�ł���킵�A��R���ڂ��ȗ����āA��S���ڂ͉����Ƃ�����킷������p���A�����Ƃ��ɂ͕��������ɏ����B
�@
11�j�����E���s�@
�@������Ȃ��ē��ɕp�x�̍������t�̓����������܂��͕��s�ɏ����ȗ��@�B�Ⴆ�Δ��R���t������b�Ȃ�n�E�i�E�\�E�_�����ꂼ������A�@��ϓ��Ȃ�L�E�L�����ꂼ�ꕽ�s�ɏ������@�ł���B
�@�Ȃ��A�u��������₩�v�Ƃ��u������������炩�Ɂv�Ȃǂ̂悤�ɔ��ɒ������߂̌��t���ȗ�������@�Ƃ��ăC�ƃX�A�q�ƃA�����������R�����Ԃ悤�ɏ����R�����@���邢�͘A���@�Ə̂���ȗ��@������B����������̌��p��Ȃ�k���@�̂P�ł���B
�@
12�j���Ȗ@
�@���X���A�u�C���c�N�L�v�̉�������킷�{���̕������Ȃ��ĐڐG�A�����A��Ԃɂ���ď������@�B�킩��₷���Q�`�R�̗�������Ă݂�ƁA�R�E�g�E�Ə����̂ɃR�̒����Ƀg��ڐG�����ė���J�M���ȗ����A�^�C�J�C�Ȃ�^�̒����ɃJ�̓���������ƌ������ė���~���Ȃ��A�Z�������Ə����Ƃ��̓Z�̒����ɂP�~�����炢�̋�Ԃ������ă��̎����������Ƃɂ���ė����~���ȗ�����Ƃ������@�ł����āA���C���E�A���E���C���X���������{�̖@�����͋ɂ߂Ĕ��W�I�ɓW�J���邱�Ƃ��ł���̂ł���B
�@
�S�D����
�@�ȏ�A��̒��������L�@�̌ւ��Ȃ�Љ�ł���B���̑��A�����A�l���l��������A���_�����@�A�����A����@�A�����@���X�A�u�ʑ����������L�@�v�Ȍ��^���Ȃ钆���������҂ɂ���ĂȂ��ꂽ�������c���Ă������A����ɂ��Ă͎����̓s��������̂ŁA���̋@��ɏ��肽���Ǝv���B�{���̐^���ɂ��ẮA���̔��\�����A�z�E�̌��ЌF�莮�n�ĎҌF�茒�i����Y�j�搶�������ɏ����āu�����a�V�Ȃ�@�����邪���ɂ��C���c�N�L�̖��p�ɂ͑��njh���̑��������A�����Ƒn�I�䔭���ɑ����o�̌h�ӂ�\���\����v�Ɛ��܂��ꂽ�̂ł��邩�A���ꂱ����m�����̖ϕ]�ƈقȂ�A�{���̐^����]�����Ă܂����Ȃ���̂���Ǝv���̂ł���B
�@�{�e�͌���ꂽ�����ƙ��X�̊Ԃɂ܂Ƃ߂����߁A���̈ӂ�s�������A�@���̐������s�\���Ȃ���̂��邱�Ƃ�{���W�҂ɂ��l�т��Ȃ��睦�M�������܂��B�i���a32�N�T��13���j
�@
�@
| �� 2005/04/03 (�run)�@�����Љ�@50�������Ɋւ�����_ |
�@�������L��������u�X�e�m�v�mo.�P�i���a32�N�W���S�����s�j�ɂ����đ��˔ɓy�i�V���[�g�n���h�j�����u50�������Ɋւ�����_�v�ɂ��ď�����Ă���܂��B�����o���͂���܂��A�P�`16�ɂ��ďq�ׂ��Ă���܂��B�������W�҂ɂ͎Q�l�ɂȂ�܂��̂ŁA���Љ�����܂��B
�@���L�����͌f�ڂ������܂���̂ŁA�u���L��{���������v�����Q�l�ɂ��Ă��������B
�@
�@���a32�N�Ɂu50�������Ɋւ�����_�v�������ꂽ���˔ɓy������ǂȂ����F���������͖ѓ�����܂���B
�@�r�c����搶�����������悤���u��S�I�����v�ł͂Ȃ��u��i�҂ւ̂��悫��Y�v���c�����߂ɁA�������W�̎������㐢�̑��L�E�֓`���邱�Ƃ͑�ςɈӋ`�����邱�Ƃ��Ǝv���܂��B
�@�������W�҂݂̂Ȃ炸���L�����z���ēǂނׂ��������Ǝv���܂��B
�@48�N�O�ɏ����ꂽ���e�ł����A���݂ł��\���ɒʗp������e�ł��B
�@
�@�@�P
�@50�������ɂ��ẮA���ɏ���y�ɂ���āA�E����_�����ɑ��錤���Ƃ��A�Z���r���Ɋւ��錤�����s���Ă����B
�@�X�@�얾���͏��a�V�N�W��29�����s�́u���L�����v��92���i���s���L���������j�Łu�����̈ꕔ���ςɂ��āv�Ƒ肵�Ę_�����A��P�}�Ɏ����悤�ȈĂ��f���Ă���B�傫���͒Z���i�E�}�Ȃǂ̋Ȃ����[�߂����̂ł���B
�@�i�����L��{���������u�������\�ۖ@�v�̃E�E�X�E�k�E���E���E�����Q�Ɓj
�@
�@���ꂪ���\���ꂽ���N�A�������a�W�N�S��15�����s�̑O�L�u���L�����v��100���̎���ŁA�l�c��ꎁ�́u���_��{�����������āv�Ƃ��đ�Q�}�̈Ă���Ă���B�u���_�l����v�Ɩ��ł��Ă���悤�ɁA������g�ő���h�������ꂽ�s�����ł���B
�@�i�����L��{���������u�l�c�āv�̃E�E�X�E�k�E���E���E�����Q�Ɓj
�@
�@������̎l����ɑ��Ĉ���������ŏ�����������̂��������Y�搶�ł���B�i�搶�͐����𐳗Y�Ɖ������ꂽ�j�u���������L�v�i�����������j�ɂ��Ɓu�E�X�k�����̑㎚�v�Ƃ��āu�ŏ����v�i�����P�~�����炢�j�ɂ��ď����A���_�ȗ��B�킩��ɂ����ꍇ�͏����~�ɂ��ď����܂��B�����ɂȂ����ꍇ�͏��J�M�����܂��B�v�Əq�ׂĂ���B��R�}�Ɏ������̂�����ł���B
�@�i���E�E�X�E�k�E���E���́A�I�E�\�E�m�E���E�����P�~�����炢�ŏ����܂��B�j
�@
�@�@�Q
�@�ȏ�͒������Ƃ��Č������\���ꂽ���̂ł��邪�A�O�q�̐X�āA�l�c�Ă̔��\���ꂽ����\�\���a�X�N�ɔ��\���ꂽ�y�c���Ȃ���̂�����B�u���{���L�������B�j�v�i�����ǖ������j�ɂ���
�@�y�c���Y���͒������̑��L�҂Ƃ��ďO�c�@�ɓ����A���ɂ��̐�������i�����ď��a�X�N�u�y�c�����L�@�v�Ǝ��Ȃ̖����������P�l�ł���B
�Ƃ���A
�@�����Ŏ��͂���ɑ听����f�s�����A���̉��ǂ̎�Ȃ�_�Ƃ��ďグ���X�̒��A��{�����Ɋւ���̂͑�R�Łu��{�����̒����y�ъp�x�����߁A�Z�W�̋�ʂ��Ȃ��������Ɓv�ɂȂ�B���̍\���̓A��×�Q���I��@�C��×�Q���G��́A�S���������̂܂܂ɂƂǂ߁A�Z����p�������߁k�`�l�y�сk�m�l����O�ƂȂ��Ă���B����ɃE��̉��_���̕₢�Ƃ��čő�������p���A�����āk�E�l�k�l�l�k���l�k���l�k���l�Ȃǂɓ��āA��ɐ���������䎮�ɂ���ď��߂ėp����ꂽ�ȉ~�I�Ȋ�{�������k�X�l�k���l�k���l�ɓ��āA��쎮�̔��~���k�k�l�k���l�ɓ��āA���ł��p�o�x�̒Ⴂ�k�~�l�k���l�ɉ������{���čs�����B�i�����̂܂܁A�������뎚�͒����j
�Ɛ����������A��S�}�̂悤��50�������������Ă���̂ł���B
�@�i�����L��{���������u�y�c���v���Q�Ɓj
�@
�@�@�R
�@�y�c����50�������ɂ́A�����ɒ������̖ʉe���c���Ă��邪�A�Z���r���A�E����_���������̌����ɓ��������̐�y�B�͂ǂ̂悤�Ȍ��_�����ł��낤���B������O���̍������i���a�U�N�Q��11�����\�j�ƍŋߒ��������番�h�����Α��P�����̐Α����߂Ă݂悤�B
�@�������ł͑�T�}�̂悤�ɃE×�Q���N�@�X×�Q���c�@�k×�Q���t�@��×�Q�����@�Ə��߂ăE���z�u�Ɋ֘A������������ق��A�����鎩�R���Ƃ����ׂ��Ȑ����}�s�ȉ��ɔz�u�����B
�@�܂��Α����͎�X���\�ȗ��ύX����Ȃ�����A���������p���������̗p����ƂƂ��ɁA�X���̎������Ȃ���̐[���Ȑ��Ƀq���g�āA������E��ɔz�����B
�@�Ƃɂ����A���̗����Ɍ���悤�ɂP���P���P��̏��P��h��50�������Ƃ��Ă̑̍ق͐����邱�Ƃ��ł����B
�@�i�����L��{���������u�������v�y�сu�Α����v�i1957�N�^�j���Q�Ɓj
�@
�@�@�S
�@���āA���͂��ꂼ��̐�y���s�������������Љ�Ă����킯�ł��邪�A��y�̌��������E����_���������̂��߁A50�����������ς���قǂ̕K�v���͍��̂Ƃ��늴���Ă��Ȃ��B�����͉��_�����k�L�@�i���̓E�X�k���������L�@�ƌĂ�ł���j�ɂ���āA���̑唼�͊ȗ����꓾��B�܂��Z���̔r���ɂ��ẮA�E����_�����قǂ̍���͊����Ȃ��B���L�����͂��̊��ԂŁA�����̐��́A�W���Ɠ��l�ɏ��L���A���ǂ��邱�Ƃ��\�ł���A���̋�ʂ����Ȃ���ΐ�Ɍ���聃�Ⴆ�A�^���i�C�ƃ^���i�C�Ȃǁ��́A�Z���ȊO�̕��@�ŋ�ʂ��邱�Ƃ��ł���B
�@�]���āA����50�������ɑ��錤���́A�ȏ�Љ�������Ƃ͈�����p�x������グ�Ă݂悤�Ƃ�����̂ł���B
�@����͕p�x�ɉ����āA�����₷������50���ɓK���ɔz�u����Ă��邩�H�̓_�ł���B
�@
�@�@�T
�@�����̎҂̂��A�������̏��̂��ꌩ���āA¯�̐������������ƕ]����B�������Ȃ���50����¯���̓T�V�X�Z�\�^�g�̂V���ɂ������A?���̓L�P��������������������11�����A®���̓t�c�A�C�E�G�I�̂V�����ł���B50���̊e�������ς��Ďg�p�����Ƃ���A¬®��¯���̎g�p����18�V�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪50�����A�悭�g�p����鉹�ƁA�����łȂ����̂���������A�Ⴆ��������Ă��A�k�L�@�◪�L�@�ɂ���ď�����Ȃ������肵�āA���ۂɂ�¬®�͐���¯���̎g�p���͓����ɂȂ�̂ł���B���\�̐������������Ă���B
�@
�i�����Ӂj
�����@�̓J�A�R�A�i�s�A�}�s�B¯�@�̓T�s�A�^�A�g�B¬�@�̓L�A�P�A���s�A���s�B®�@�̓A�s�A�t�A�c�B���̓N�A�`�A�e�A�n�A�q�A�w�A�z�̊�{�����̕�����\�L���܂��B�i���� �o�j
�@
�@�� �� �\
�@�@�@�@�ʑ����������L�@�@���������L�@�@���L�̊�{����
�@�@�@�@�i�����������j�@�@�i�����������j�i�����m�q���j
���@���@�@�@33�@�@�@�@�@�@�@21�@�@�@�@�@�@�@27
¯�@���@�@�@36�@�@�@�@�@�@�@20�@�@�@�@�@�@�@40
®�@���@�@�@20�@�@�@�@�@�@�@�W�@�@�@�@�@�@�@16
¬�@���@�@�@21�@�@�@�@�@�@�@10�@�@�@�@�@�@�@25
���@���@�@�@33�@�@�@�@�@�@�@14�@�@�@�@�@�@�@11
�i�e�����̍Ō�Ɍf����ꂽ���L����ɂ���ē��v�����j
�@
�@�ȉ��ɕp�x�Ƃ��k�L�A�ȗ��@�Ƃ͂����A�͂�50���������V����������߂Ă��Ȃ�¯�����A18����������¬®�Ɠ������Ŏg�p����Ă���Ƃ������Ƃ́A¯���Ă��T�V�X�Z�\�^�g�̕������悭�g���邱�Ƃ��Ӗ�������̂ł͂Ȃ��낤���B
�@����ł́A¯��¬®���́A�ǂ��炪�����悢���Ƃ������ɂȂ��Ă���B¯����¬®���ɏ����ď����₷���Ƃ���Ȃ�A��������50�������́A���̕����̕p�o�x�i���ł͂Ȃ��A�����́j�ɓK���ɔz�u����Ă���ƌ�����ł��낤�B¯�����i����{�����̃^�A�V�j�Ȃǂ̒Z���́A���قǏ��L���Q�����Ȃ����A���̑��̕�����¬®���̂ǂ̕������������ɂ�����������̂́A���P�l�ł͂���܂��B
�@�Ƃ���A�g�p�x���̑����T�s�𒆐S�ɂ���¬®�������������悤�ɉ��҂��邱�Ƃ́A�ʂ����ĉ\�ł��낤���B���͗��_�I�ɂ͉\�ł���Ǝv�����A���Ă��������Ƃ��ł���B�������A����50�������̉��ψȏ�ɖ��Ȗ�肪�N�����Ă���B���̖��Ȗ��Ƃ͉����B����ɑ��鎄�̌����͂ǂ��Ȃ̂��B�܂������̖�肩�疾�炩�ɂ��Ă������B
�@
�@�@�U
�@����ł́A¯����¬®���́A�ǂ��炪�����悢���Ƃ������ɂȂ��Ă���B¯����¬®���ɏ����ď����₷���Ƃ���Ȃ�A��������50�������́A���̕����̕p�o�x�i���ł͂Ȃ��A�����́j�ɓK���ɔz�u����Ă���ƌ�����ł��낤�B¯�����_�j�@�Ȃǂ̒Z���́A���قǏ��L���Q�������Ȃ����A���̑��̕�����¬®���̂ǂ̕������������ɂ�����������͎̂���l�ł͂���܂��B
�@�Ƃ���A�g�p�x���̑����T�s�𒆐S�ɂ���¬®�������������悤�ɉ��ς��邱�Ƃ́A�ʂ����ĉ\�ł��낤���B���͗��_�I�ɂ͉\�ł���Ǝv�����A���Ă��������Ƃ��ł���B�������A����50�������̉��ψȏ�ɖ��Ȗ�肪�N�����Ă���B���̖��Ȗ��Ƃ͉����B����ɑ��鎄�̌����͂ǂ��Ȃ̂��B�܂������̖�肩�疾�炩�ɂ��Ă������B
�@
�@�@�V
�@�����u���L����v�̑O�g�ł���u���L�v�̂R���i���a24�N�U�����j�ŋ���{���̒r�c���ꎁ�́A���̃g�b�v�L���Łu�������\��Җ]���v�Ƃ��āA���̂悤�Ȉꕶ�\���Ă���B
�@
�@�ǂ���珑������x�ɏ�B����ƁA�قƂ�ǑS�Ă̐l�X���������L�Ɍg����Ă₪�Đ�呬�L�҂ւ̓r�����ǂ�A���̒��łق�̏����̐l�X������ɐi��ō����̌����ւƎu���Ă����B
�@���̍s�����̑���ɂ���Č����̕������������Ă���B�O�҂͐���{�����A���邢�͊�{�V�X�e���͂��̂܂ɂ����������̍H�v�A���P�ւƔ�r�I���Ղȕ�����I�сA��҂͊�{�����A���邢�͊�{�V�X�e���܂ł����̂ڂ��ė��_�I���ς̕����ւƐi��ł����悤�ł���B�i���j����͋ɂ߂ď����̂悤�ł���B
�@�Ȃ��Ȃ�P�̕����Łi���j�n�B�������̋Z�p�������ė��_�I�Ɋ�{�����A���邢�͊�{�V�X�e����S�ʓI�ɉ��ς���ɂ́A�����g�ݗ��Ă�܂łɑ����̎�����v�������ł͂Ȃ��A����ɗ��K�A�C�n�܂łɒ��N�����₳�Ȃ���Ȃ�ʂ��A�����������ǂ����听�����Ƃ��Ă��A�䂪���z�E�̌���ł́A����������ĂP�̌��Ђ��鑬�L�����ɂ܂Ŕ��W�����߂邱�Ƃ͋ɂ߂Ď���ȋƂł��邩��ł���B
�@���ƂȂ�P�����Ƃ��ĎЉ�I�M�C��ɂ͏o�ŁA�w���A��`���X�o�ϓI�ɂ��A���_�I�ɂ�����}�f�̂Ȃ����Ȃ�����ȕ��S�ł���A�����Ă�������Ȃ�������������N�����₵�đ听������S�̌����������k�ɕ����I���݂ɏI���Ƃ������ʂɂȂ邩��ł���B
�@
�@����50�������ɂ܂ł����̂ڂ��āA���̉��ς�_���Ă���̂ł��邪�A�܂��ƒr�c���̌����悤�ɁA����́u����̋Ɓv�Ȃ̂ł���B
�@
�@�@�W
�@�����̌��������\����Ȃ�����A50�������Ɋւ��錤���͔��ɏ��Ȃ��A�܂��������Ƃ��Ă��A�ŏ��ɏЉ���悤�ɁA���^�̖ʉe������Ȃ����x�̂��̂ł���̂͂Ȃ����낤�B�r�c���̌����悤�ɇ@�V�����V�X�e���ɏK�n����̂��܂����A���ɎЉ�I�M�C�邽�߂̌o�ρA���_���ʂɂ킽���J�̓_�A���̂Q�̓_���A������Ȃ����߂Ȃ��̂ł��낤�B��ɐV�����V�X�e��������o�����߂ɂ́A����̗��_�����ł͂��߂ŁA�����Ҏ��g�������x�̑��L���ł��Ȃ���Ȃ炸�A�����ɂ��Ă���ꍇ�ɂ́A50���������P�����ł����ς��悤���̂Ȃ�A�����ɍ����x����̂ŁA���X���Ȃ̏C�߂������ɕs�ւ������Ă��A�ڂ��Ԃ��Ă��܂��̂�����ł��낤�B
�@����Ɏ��͒r�c���������Ȃ������A�����P�̃u���[�L�����݂��邱�Ƃ�ے�ł��Ȃ��B����͂��ĐX�@�얾�������݂��������̒����u�����������L�@�v�ŏq�ׂ��悤�ɁA���Ȃ����ݏC�߂Ă�������̑n�Ď҂ɑ��鐸�_�I�ȂȂ���̖ʂł���B�X�@�얾�����q�ׂ��ꕶ�����p���Ă������B
�@
�@����50���}�ɑ��Ă͔��Ɍh�ӂ��A�i�v�ɕύX���Ȃ��Ƃ������Ƃ�������X�w�k�̋`���ł���˂Ȃ�ʁB�����Ȃ鎮�ł�50���}�͑n�Ĉȗ����т��щ��ς���Ă���B�n�Ď҂��ύX����Ίw�k�����ς���B������ɒ������ɂ����Ă͔��\�ȗ�17�N���i�M�Ғ������݂ł�40���N�ԁj�P��̉��ς����Ȃ��B����͔��ȋ��݂ł���Ǝv���B��킭����ƂĂ������̕s�ւ͂����Ă��i�v�ɉ��ς���ꂴ�ނ��Ƃ��A����n�Ď҂ɑ��鉽���̋L�O��ł���A�Ӊ����ł���B
�@
�@�@�X
�@�^�̌����Ƃ������̂́A�o�ϓI�A���_�I�ʂɍS�����ꂸ�A�������_�I�ɋ���������̂łȂ���Ȃ�ʂł��낤�B���������ɂ͂����܂œP����Ȃ��コ������B�O�Ɉ��p������y�B�̌��t�́A���ɂ͑����ȃu���[�L�ƂȂ��Ă̂�������B��������̌�y�ɑ��L���w������ꍇ�A�����ɂ���ΒZ�����Ŋ��������邩�A�����Ə����₷�������͂Ȃ����Ƃ������Ƃ������痣��Ȃ��B���͂����ő傫�ȃW�����}�̒J�ɗ�����̂ł���B
�@���͂��̒J��ł����l����B����ɏ����₷������������Ƃ���A����������Ă����̂����A�u�n�Ď҂ɑ��鉽���̋L�O��ł���Ӊ����Łv�͂Ȃ����낤���A�ƁB
�@���ꂪ����ʂ��A���͍ŏ��ɑ��}�Ōf�����X�@�얾���̃E�����ψĂ̔��\�ɓ������āA�X���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@
�@���܂ł��s�ւ�E�т����̓�����g���Ă��邱�Ƃ͍l�����̂ł��邩��A�ǂ��܂ł����L�����͑��L���铹��ł���Ƃ������n�ɗ����Ď��p�ɑ����ď��X�ɉ��ς��������X�Ɋo���₷�������₷�����̕����̊ȒP�ɂ��Ď��p��ł��K����悤�ɂ��Ă����Ƃ������Ƃ͉��������̂ł���Ƃ����C�f�I���M�[�ɂƂ��ꂴ����肱��͉��̏�ɐS���Ēu���ׂ����Ƃł���Ǝv���B
�@
�@�@10
�@����͐X�@�얾�����A���̒����u�����������L�@�v���Ҋ�{�������͂�50���}�ŁA�u��킭����ƂĂ������̕s�ւ͂����Ă��i�v�ɉ��ς���ꂴ�ނ��Ƃ��v�ƌĂт����u����n�Ď҂ɑ��鉽���̋L�O��ł���Ӊ����ł���v�ƒf���Ă���P�N��̂��Ƃł���B���͂��̑S�������������t���A������P�N��ɏq�ׂꂽ�Ƃ������ƂɁA��������͂��Ȃ��B�X���́u�����������L�@�v�̒��Łg���ς��Ȃ��悤�h�Ăт������Ƃ��A���Ɍ��݂̎��Ɠ����悤�ȃW�����}�Ɋׂ��Ă����ɈႢ�Ȃ��B�����Ď��͎����̐S�̔Y�݂Ɏ���I�~����łƂ��Ƃ��āA���������ꕶ���������̂ł͂Ȃ��낤���B�������A����ł��Ȃ����̌�������S���~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł���B���͂��̂P�N�Ԑ����Ƌꂵ���Ƃł��낤�B�����ď��a�V�N�W�����}�̈Ă��X�ň��p�������͂ƂƂ��ɔ��\����ɂ͑����̗E�C���K�v�������낤�Ǝv���̂ł���B
�@
�@�@11
�@�X���̏��a�V�N�W���̉��ς̕ق̒��ɁA���͂����P�����^����c�����̂ł���B����́u���������̂ł���Ƃ����C�f�I���M�[�ɂƂ�킴�����v�u���X�ɉ��ς������v��Ƃ����������Ȃ̂ł���B�����Ȃ̏C�߂��������痣��邱�Ƃ�O��Ƃ��ā��Ƃ����ӂ��ɂ��̌��t�����̂͌���Ă��邾�낤���B���⎄�͐X�������������番�h���邱�Ƃ�O��Ƃ����Ƃ��A�ǂ����Ƃ��Ƃ��������������Ƃ���̂ł͂Ȃ��B��ʘ_�Ƃ��āu�������Ƃ����C�f�I���M�[�ɂƂ��ꂴ�����v�����������Ƃ��������̂ł��낤���B�C�f�I���M�[�ɂƂ����҂́A���ꂶ��ǂ��Ȃ�̂��낤�B���͐�Β��������Ƃ����C�f�I���M�[��ς��Ȃ��B�����A����50�������ɂ܂ŗ��������Ă̌�������肽���̂ł���B
�@�����ŁA�܂��V������肪��N�����B50�������̉��ς͕��h���Ӗ����A�V���������̒a���ƌ�����̂��ǂ����A�Ƃ������ł���B
�@
�@�@12
�@���ɁA������50���������������ς��āA����ȏ�̖@���͊����̂�������Ɖ��瑊��Ȃ����Ă�����Ƃ���B��������ƌ���ł��낤���B�V�����ƌ��Ȃ����낤���B����Ƃ����������̈��E���ʂ��̂ƌ��Ȃ����낤���B�܂�ŃR�E�����I�ȕ����ɂȂ肻���ł���B�܂�50�������͂��̂܂܂ŁA����ȏ�̖@�����A����Ă��鎎�Ă�����A����͂ǂ����낤�B50����������������Ă��āA���̏��@�����������Ƃ������Ƃ́A���蓾�Ȃ��ƁA�ȒP�ɂ͕ЂÂ����Ȃ��B���@���ɂ͉��ς̗]�n���Ȃ����A50���������ɂ͂ǂ������S���Ȃ���������Ƃ������Ƃ͍l�����邱�Ƃł���B��ɍŋ߂̂悤�ɂ��낢��̌���������ɂȂ�Ə��@���͑�̎�����������̂��̂ɂȂ��Ă���B���܂ŋ֒f�̉��Ƃ��ꂽ50�������ɁA�����̃��X���������Ȃ��ƁA���ꂪ�f���ł��悤�B�����l����ƁA�V���������Ƃ��A�����łȂ��Ƃ�������́A�P��50�������݂̂ɂ���Ĕ��f����Ă͂����Ȃ��Ƃ������_���o��̂ł͂Ȃ��낤���B
�@
�@�Ȃ�ق�50�������Ŕ��f����̂́A�ł������葁�����Ƃł͂���B���������l�Ԃ̊�̂悤�Ȃ��̂ł���B�����������b���A���`��p�Ȃǂ����B���āA����l�ł����Ⴆ��悤�Ȋ痧���ɂȂ邱�Ƃ��ł���B�v��50���������珔�@���Ɉ�т��ė����u���Ă̍��{���_�v�Ƃł��������̂f�̎ړx�Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂��B50�������͓���ł��\�\��A�`�͑O�ƕς��Ȃ��Ă��A���@��������Ă���B���_������Ă���A���͂�V�������ƒf���ׂ��ł͂Ȃ��낤���B
�@
�@�@13
�@����{�����̒r�c���ꎁ�́A��N��10��20���ɊJ���ꂽ���{���L�����Q��ψ���ŁA�ψ��̈���Ƃ��ē��������E��������ɓ�����
�@
�@����n���̕����ł����āA�����������̉��ς��s�����ɂ����Ȃ����̂������ā������Ɩ�����Ă�����̂����邪�A����͐��E��������̏ꍇ��ɗ��ӂ���悤�ɁB
�@
�Ƃ̈ӌ����q�ׂĂ���B�u�������̉��ρv�Ƃ́A�ǂ̒��x���w���̂ł��낤���B50�������̉��ς��܂߂Ă̂��Ƃ��낤���B�i�ꕔ�̈ӌ��Ƃ��āA50���������P�^�R�܂ł̉��ς͓�������ƌ��Ȃ��Ƃ����Ă���������ɋL������j�܂��A�������̉��ςɂ���ā������Ɩ�����Ă�����̂́A�V�����Ƃ��Ắ�������F�߂��A�ꎮ���𖼏��Ƃ����̂��A����Ƃ��������Ɩ���点�Ă͂������A���������E�����ɂ͂��Ȃ��悤�ɁA�Ƃ����̂��B���́���������������`�����i�҂����o���A�����Ƃ��o���Ƃ��Ă��c�c�B
�@
�@�@14
�@�u���{�̑��L�v�̖{�N�U�����ŁA����{�����̒r�c���ꎁ�́u�䂪���̌ւ�ȗ��@�v�Ƃ����_�����f��
�@
�@�����������t������킷�����̉Ȋw�I�����Ɏn�܂�A�����̐��i�𖾂炩�ɂ��āA�܂��@�����l�Ă��A���_�I�{��Z�k�ɕK�v�Ȃ�50���̔z������̌�Ɍ��肵���Ƃ����Ƃ���ɁA���������ݗ��̂��̂Ƃ��̗��Ă̍��{���_���قɂ��Ă��邩��ł����āc�c
�@
�Əq�ׂĂ���A���ꂱ���u�n�Ď҂̖��̂������Ă͂���Ȃ����������L�@�̒���������䂦��̑�����Ƃ���v�ƌ����Ă���̂ł���B���Ƃ���A�������ɂ����ẮA50�������́A���̗��Ă̍��{���j�������邽�߂̈��i�ł����āA��Ȃ��Ƃ�50���������P��ł�����������Ƃ܂ŋɌ��ł���̂ł͂Ȃ��낤���B
�@
�@�@15
�@���āA���͂��낻�댋�_���}���˂Ȃ�Ȃ��B���_�I��50�������̉��ς͉\���Ƃ��Ă��A�܂����̑O�Ɍ��s¯���ɓ��Ă����\�\�T�V�X�Z�c�c�^�g���A¬®���ɒu�������āA�ʂ����Ă��̘A�ԂɌ��s�ȏ�̌��ʂ������邾�낤���B�n�Ď҂͂킴�ƃT�V�X�Z�\�^�g������킷������¯���ɒu���āA�����I���o�ɋ߂Â��悤�Ƃ����̂ł͂���܂����B�i������¯����45�x���ł������̂𐳗Y�搶�ɂ��30�x�ɉ��߂����Ƃ́A�����I�Z���X�ւ̈ڍs�ƍl�����ʂ��낤���j����¯��¬®�̉���u�����������������Ƃ��āA���������ꂪ�������Ƃ��ĕ��y�����Ƃ��āA���s�����Ŋw�K���A�܂������ɂ��Ă���҂Ƃ̒������ǂ����邩�B���ݔ��s���̋��ȏ����ǂ����邩�B�l����꓾�邢�낢��̍����ɂǂ��Ώ����邩�B�l����l����قǁA50���������߂�����_�͑傫���[���̂ł���B
�@
�@�@16
�@�Ō�Ɏ��́A�{�����r�c���ꎁ��24�N�U���́u�������\��Җ]���v�Ƃ������͂̌��т����p���Ă��������B
�@
�@�������Ȃ���z���Ɍg����Ă��̉��b�ɐ�����҂Ƃ��āA���̂�����̕����i�����k�L�A���L�@�̌�����50�������ɂ܂ŗ������錤���j��I�Ԃɂ��Ă��A���߂ɂ����S�I�����ł͂Ȃ��A��挩�n����A��p�҂ւ̂��悫��Y�Ƃ��āA�Ђ��Ă͉䂪�����L�E�̌��㔭�W�Ɋ�^����Ӗ��ɂ����Đ^���Ȍ������\��ؖ]���Ă�܂Ȃ����̂ł���B
�@
�@�܂��Ɓu���߂ɂ����S�I�����v�ł͂Ȃ��u��i�҂ւ��悫��Y�v�Ƃ��ẮA50�������ɗ��������Ă܂ł̌������A���̎����ʂ��ĂȂ���邱�Ƃ��A�����ؔO����B
�@�u��i�҂ւ̂��悫��Y�v�Ƃ��Ắu�X�e�m�v���炵�߂����B���̈Ӗ��ŁA���͂����Ė�葽��50�������ɂ��Ă̌����ւ̃q���g�Ƃ��̏�Q���N���Ă݂��̂ł���B
�@
�i���a32�N�V���S���j
�@
�@
| �� 2005/03/28 (�lon)�@�T�E�X�|�[�p�̑��L |
�@���L�E�̑��y�E���q��������A�T�E�X�|�[��p�̃z�[���y�[�W�����Љ�������܂����B
�@
�@�A�����J�̂fregg���ł��B
�@
�@�keft �rhorthand �aook �ɂ́A�keft �uersion �� �mormal �uersion ���Љ��Ă���܂��B
�@
�@�keft �rhorthand
�@http://www.werelight.com/shorthand/
�@
�ł��B�܂��䂪���ɂ̓T�E�X�|�[�p�̃e�L�X�g�͂���܂���B������������́A�T�E�X�|�[��p�̃z�[���y�[�W�����E�߂������܂��B
�@
�@
| �� 2005/03/27 (�run)�@���L�����̂܂Ƃߕ� |
�@���L�����̂܂Ƃߕ��ɂ͉��L�̕��@������܂��B
�P�D�P�̑��L�@�̌n����{�̌n�ɂ��Ă��낢��ȏ���������悹���č쐬������@�B
�Q�D�P�̖@���̌n�����̂܂܂̑̌n�ō쐬������@�B
�@
�@�P�D�̍쐬���@�͂��낢��Ȗ@����@�����Ƃɏo�T�𖾂炩�ɂ��ĂP���̎����Ƃ��Ă܂Ƃ߂Ă������@�ł��B
�@�Ⴆ�A�����@���ł��A�`�̑̌n�A�a�̑̌n�A�b�̑̌n�Ƃ����悤�ɂ܂Ƃ߂Ă������@�ł��B
�@�����쐬���������ł́u���������L�@�̌n�v���������܂��B
�@
�@�Q�D�̕��@�͊e�@����n���P�����ɍ쐬������@�ł��B���̖@���̌n�����Ȃ��Ŏ��������̂܂܍쐬������@�ł��B
�@�����쐬���������ł́u���������L�@�����ҁv�P�`13���ɑ������܂��B
�@
�R�D�������g�p���Ă���̌n���܂Ƃ߂����̂ł��B�`�̑̌n�A�a�̑̌n�A�����ōl�����������Ȃǂ�ܒ������̌n�ł��B�����쐬���������ł́u�m�`�j�`�m�d �jurzschrift�v�y�сu���������L�@�����v������ɑ������܂��B
�@
�@�����ŁA�d�v�Ȃ��Ƃ́A���̖@���̌n�͂`�̑̌n�A�a���̌n�Əo�T�𖾂炩�ɂ��Ă������@�ł��B
�@
�@�܂��A���L�̎������쐬����ꍇ�ɂ́A������x�̋��ʂ����`�ɂ��Ă������Ƃ��K�v�ł��B
�@���Ɂu���������L�@�����ҁv�P�`13���̂悤�ȃV���[�Y���̂ɂ́A���ʂ����`�ɂ��Ă������Ƃ��K�v�ł��B
�@
�@�쐬�����������R�s�[�@�ŃR�s�[�����Ƃ͔���Ȏ��Ԃ�������܂��B��x�A�쐬���������𐔕��R�s�[���鎞�Ԃ͔���ł����A�o�c�e�łƂ��ĕۑ����Ă����Ƃb�c-�q�ɏĂ����鎞�Ԃ͒Z���Ԃōς݂܂��B
�@�ŏ��̂o�c�e����Ƃ͔��Ɏ��Ԃ�������܂����A��X�̂��Ƃ��l����Έꎞ�I�ȍ�Ƃł��B����10�y�[�W����Ƃ��s����10���������100�y�[�W�̍�Ƃ��I���܂��B
�@100�y�[�W���P���ō�Ɗ���������Ǝv���ΐ��_�I�ɂ���ɂɂȂ�܂��B
�@
�@���a59�N�V���Ɂu���������L�@�̌n�v��20���R�s�[��Ƃ����܂������A�a�T�ł�374�y�[�W�i�����ł�415�y�[�W�j�ł������A�R�s�[�@�������Ă��Ȃ������̂ŁA�X�ŃR�s�[�����܂����B�r���ła�S���̗p�����Ȃ��Ȃ�R��ɕ����ăR�s�[���܂����B�R�s�[���P��10�~�������Ǝv���܂��B
�@�a�S���̗p�����Q�܂�ɂ��Ē�����ƁA���{��Ƃ����܂����B���{�̓p���`�Ō����J���ăt�@�C���R���ɕ����܂����B
�@�o�c�e�łł�25.6�l�a�ł��B�b�c-�q�P���ɏĂ����鎞�Ԃ͖�R�����炢�ł��B
�@���Ȃ݂ɖ�150�l�a�i�a�T�łŖ�2600�y�[�W�j�̗e�ʂ��b�c-�q�ɏĂ������Ǝ��Ԃ͖�S�����x�ł��B
�@�P���Ԃ������10���ȏ�͏Ă������ł��܂��B
�@�o�c�e�t�@�C���̍ő�̓����́A
�P�D������Ȃ��B�ꏊ�����Ȃ��B
�Q�D�Z���Ԃłb�c-�q�ɏĂ�����Ƃ��ł���B
�R�D�����������B�����������B
�S�D�]���ȍɂ�����Ȃ��B
�T�D�P���̂b�c-�q������ΊȒP�ɃR�s�[�ł���B
�@
�@
| �� 2005/03/26 (�rat)�@�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l |
�@
����16�N12��22��
���c�@�l�Љ�ʐM���狦��
��@���@�{�@���@�@�i
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�l�ރo���N�ψ���
�ψ����@��@�o�@�@�v
�@
��T���u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�����\�̒�o�ɂ���
�@
�@������ł́A����13�N�x���當���Ȋw�ȂƋ��c���u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�Ƃ����̍����x���߁A�S���e�n�̐��U�w�K�C���X�g���N�^�[�̊F�l�ɁA���̏̍���t�^���鎖�Ƃ�i�߂Ă܂���܂����B
�@�����Ŗ{�N�x���u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�̑I�l��i�߂����ʁA���Ȃ��l���T���u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�̔F�،��҂Ƃ��Đ������邱�Ƃ����肵�܂����̂ł��m�点�������܂��B
�@���܂��ẮA��T���u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�Ƃ��ĔF���Ă��������������肢����ƂƂ��ɁA�������[�̐܂�Ƃ͑����܂����A���̔F�ɕK�v�ȕʎ��u�����\�v�ɂ��L��������������o�����肢���鎟��ł��B
�@�i�ŏI����́A���c�@�l�Љ�ʐM���狦���A�Ȃ�тɐl�ރo���N�ψ���łP�����{�ɐR������J����������̉^�тƂȂ�܂��̂ŁA���������������B�j
�@���̔F�ؐ��x�́A���U�w�K�C���X�g���N�^�[�̒�����A����w�Ԃ��Ƃ��p�����A��|�ɏG�ŁA����Ƀ{�����e�B�A���_�������ŁA�n���w�Z���Ŋ�����т̂������I�o���A�u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�Ƃ��ď̍���t�^���Ă�����̂ł��B����13�N�x����n�܂��Ĉȗ��A�S����891���̕������łɔF���Ă���܂��B���Ȃ����h�_����F���A���U�w�K�Љ�̔��W�E���i�ɂ����p����������Ɗ肤����ł���܂��B�Ȃ��A���̔F�Ɋւ����p�͈������܂��Ƃ�\���Y���܂��B
�@�ȏ�A��|���������̏�A�ʎ��u�����\�v�ɂ��L���̏�A�܂�Ԃ����ԑ����������B�܂��F�؎����A����17�N�T��26���i�y�j�����E�z�e���I�[�^�j�ɂčs���܂��B���̔F�؎��ւ̏o���̂��\������킹�Ă��m�点����������K�r�ł��B
�@�Ȃ��A��T���u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v���薼����쐬���A�����Ȋw�Ȑ��U�w�K����ǂ��A���ȓ��̋L�҃N���u�ɔz�z���A�S���ɂ��܂˂����m���Ă���������悤���\���Ă���܂��̂ŁA���������������B
�@
�Ƃ������ނ����c�@�l�Љ�ʐM���狦���͂��܂����B
�@
�@
�����\�u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v����
�@�����^���ʁ^�N��^�w������^�C���X�g���N�^�[�o�^�ԍ��^���N�����^�N��^�Z���^�d�b�E�e�`�w�^�d���[���^�Ζ���E��E�@�Z���^������ȊO�̎��i�E���Z�Ȃǂ��L�������������B�^�{�����e�B�A�I�v�f�̂���Q���B��Òc�̖��E��E�����L�����Ă��������B�^���̊Ԃ̐��U�w�K���i�����L�^�B�n�抈���L�^��w�Z�����x�������ȂǁB
�@
�Ȃǂ��������ޗ�������܂��B���̎w������́u���U�w�K�v�ł����A�C���X�g���N�^�[�o�^�ԍ��́A���U�w�K�P���C���X�g���N�^�[�i���U�w�K�j�̎��i�ɋL�ڂ���Ă���܂��B
�@�܂��w������ȊO�̎��i�E���Z�́u���L�v�ӊO�Ɏ����Ă���܂���B
�@�{�����e�B�A�I�v�f�̂���c�̂́A�Вc�@�l���{���L����������C�u�����A���A�Вc�@�l���{���L����k�C���x�����U�w�K�S�������A�k�C�����L�m��������S�������A����n�搶�U�w�K�C���X�g���N�^�[�̉���ǒ����炢�ł��B
�@���̊Ԃ̐��U�w�K���i�����L�^�́A������Ȃ��̂Łu�ʎ��v�ɂ��܂����B
�@
�@�����������u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�̒����\�ɂ͕ʎ��ʼn��L�̂��Ƃ������܂����B
�@
��啪��^�u���L����v�y�сu���L�����v
��U�Ȗځ^�u���L�j�i���{�j�j�v�y�сu���L�����w�v
�@���w�E���Z���ォ��ƏK�E�ʐM����ŁA����c���y�ђ������̒ʐM������I�����Ă���܂��B���Z���ƌ�́A�����̒������L�w�Z�i�w���đ��Ƃ��Ă���܂��B�܂��������L�w�Z�ł͖�ԕ��̍u�t�����Ă���܂��B
�@���͖�40�N�ԑ��L���w��I�ɒNj����Ă��܂������A�����ɂ��낢��ȑ��L�W�̕������̎��W���s���āA���L�W�̎��������쐬���ăR�s�[�Ȃǂő��L�W�@�y�ё��L���Ԃɖ����Ŕz�t���Ă���܂��B
�@���܂ő��L�E�Ŋw�K�y�я����W�����m�����������������邽�߂Ƀz�[���y�[�W�u���L���y�v���J�݂��āA���L�̊y�����Ȃǂ�`���Ă���܂��B
�@�z�[���y�[�W�́A���L����D���Ȓ��ԂƗ����グ�܂����B�����Ǘ��l�����Ă���܂����A�Ǘ��l�́u���e�쐬�v�A���_�́u�z�[���y�[�W�쐬�v�ƁA��ƂS���Ă���܂��B
�@���L�T�C�g�Ƃ��āA���߂ē�l��g�̊����ȕ��Ɖ��̐���z���グ�Ă���܂��B
�@�l�̃z�[���y�[�W�ł́A�����ł͂Ȃ��������ݓ��̓n���h����������ɂȂ��Ă���܂��B���̏ꍇ�͑��L�E�Ŗ{�������y���l�[���E���� �o�ł��ʂ��Ă���܂����A���L�W�̋@�֎����ɂ��y���l�[���œ��e���Ă���܂��B�n���h�������u�Ǘ��l�v���g�p���Ă���܂����A���L���Ԃ��^�c���鑬�L�T�C�g�i���L�w�K�Ґ�p�j�ƘA�g���Č��e����Ă���܂��B
�@�z�[���y�[�W�̖��̂́A�ꌩ�ӂ������悤�Ȗ��O�����Ă���܂����A���g�͂��Ȃ�ł����̂ł��B�{���Ώێ҂͓���҂���v�����L�ҁE�w���ҋy�ь����҂܂ŕ��L�����e�ł��B
�@
�u���L���y�v
�@�t�q�k�@http://www12.ocn.ne.jp/~sokkidou/
�ł��B���̑��L�T�C�g�Ɣ�r���Ă��A�f�ڂ��Ă��錴�e�͓��e�I�A�Z�p�I�ɂ������͂��Ȃ��ƍl���Ă���܂��B
�@
�@�܂��A�n���ɂ����ẮA����n�搶�U�w�K�C���X�g���N�^�[�̉�̎����ǂ�S�����Ă���A����16�N10��17���Ɉ���n�搶�U�w�K�C���X�g���N�^�[�̉��ÂŁu���L����u���v���s���܂����B
�@����s����ψ���U�w�K�ہu���U�w�K���v�ł́A���L�̍u�t�Ƃ��ēo�^���Ă���܂����A����s�ߍx�ł͑��L���w�K�������Ƃ�����]�҂����Ȃ��̂ŁA�n������肵�Ȃ��Ńz�[���y�[�W�u���L���y�v��ʂ��Ċ������Ă���܂��B
�@�z�[���y�[�W�ł́A�����g�p���Ă��钆�����𒆐S�Ɍf�ڂ��Ă���܂����A���L�̃e�L�X�g���Ń_�E�����[�h���ł���悤�ɂ��Ă���܂��B
�@�܂��A���Z�{�����e�B�A�Ƃ��đ��L����R�[�X��݂��Ă���܂��̂ŁA��]�҂ɂ͓d�q���[���y�ё��L����������ꍇ�ɂ͉摜�t�@�C�����쐬���ēY�t�t�@�C���Ŏ��ⓙ�ɉ����Ă���܂��B
�@
�@���L�E�ł͎Вc�@�l���{���L����������C�u�����A���Ƃ��āA���L�W�����ژ^�̒�����S�����Ă���A���a58�N�̓��{���L���\100�N�L�O�y�ѕ���14�N�̓��{���L120�N�L�O�ɂ́u���L�W�����ژ^�v��ƂɌg����Ă���܂��B
�@�Вc�@�l���{���L����k�C���x�����U�w�K�S�������Ƃ��āA���L�U�w�K�̗��ꂩ�瑨���ăz�[���y�[�W�u���L���y�v�ő��L�̌[�֊�����W�J���Ă���܂��B
�@
�@�ȏオ�u���̊Ԃ̐��U�w�K���i�����L�^�v�̕ʎ��ł��B���̒a�����P��12���ɏ��ނ��o���܂����B
�@
�@
�@
����17�N�P��20��
���c�@�l�Љ�ʐM���狦��
��@���@�{�@���@�@�i
�@
�u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�F�ɂ��āi����ʒm�j
�@���āA��T���u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�I�l�R����ɂ����܂��āA���Ȃ��l���u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�Ƃ��ĔF���邱�ƂɌ��肢�����܂����B�܂��Ƃɂ��߂łƂ��������܂��B
�@�S��肨�j����\���グ�A���A���Ƃ������܂��B
�@
�i�����j
�@�Ȃ��A�����Ȋw�Ȃł́u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�̎�|�ƍ���̐��i�̐��A��T���̒B�l�̕��X�̂����O�E���Z���Ǝw������E���i���Z�����A�ߓ��A�L�Ҕ��\����\��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�\���Y���܂��B
�@
�@
��T���u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�F�؎�
�@�@���@���F����17�N�Q��26���i�y�j11�F00�`11�F45
�@�@��@���F�z�e���j���[�I�I�^�j�@�Ă̊�
�@�@�@�@�@�@�@�����s���c��I���䒬�S�|�P
�@�@��@���F���c�@�l�Љ�ʐM���狦��
�@
�@���@���@��
�@���������@���c�@�l�Љ�ʐM���狦���@�{�@���@�@�i
�@�F�؎��^�@�u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�F�؏�@�{�@���@�@�i
�@�j�@�@���@�����Ȋw�Ȑ��U�w�K����ǁ@���U�w�K���i�ے��@��@���@�@��
�@�@�@��
�@
�@
�@�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�́u�F��؏��v�ɂ́A���L�̓��e���L�ڂ���Ă���܂��B
�@
�u�F��؏��v
�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l
�@�@�@�@���@���@�@�@���a
�@���Ȃ��͐��U�w�K�C���X�g���N�^�[�Ƃ��Đ��U�w�K�̐��i�ɐs�͂���܂����w�Z�T�T�����̎��{�ɔ����n���w�Z�ɂ�����q�ǂ������̂��悫�x���҂Ƃ��Ċ��҂������Ɂu�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�̏̍���t�^���F���܂��B
�@����17�N�Q��26��
�@�@���c�@�l�Љ�ʐM���狦��
�@�@�@�@�@�@�� ���@�{�@���@�@�i
�@
�@
�@
�@
�@����16�N�x�̑�S���u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�ł�104�����F����Ă���܂��B
�@�܂��A��T���u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�F�؎Җ���ɂ�230�����f�ڂ���Ă���܂��B
�@����17�N�Q��26�����݁A�u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�͍��v1,121�����F����Ă���܂��B
�@�u���U�w�K�P���C���X�g���N�^�[�v�̗L���i�҂̎w��������킸�I�l�̑ΏۂɂȂ�܂��B
�@���͎w�����삪�u���U�w�K�v�ł��̂ŁA�����̓��ӂȂ��̂��w���ł��܂��B
�@
�@����17�N�P���T�����݁A���U�w�K�C���X�g���N�^�[�o�^�҂́A22,070������܂��B
�@���U�w�K�P���C���X�g���N�^�[�c�c3,887���B
�@���U�w�K�Q���C���X�g���N�^�[�c�c18,183���B
�@
�@�w������������n�����i���v�A�Z���A���U�w�K�A�ИJ�m�A�q���Ǘ��ҁA���@����A�}�l�W�����g��b�A������Ɛf�f�m�A�C���X�g���N�V�������X�j�A�Z�p�n�����i�d�C�E�d�q�A�n���Ȋw�A�����~�́A�ƒ뉀�|�A�V�Ɠd�C���Z�m�A�����A��A���i�ʐ^���X�j�A�����Z�p�E���{�����i�h�{�Ɨ����A�����A�����́A�p��A�����A�y���K���A�Õ����A�����A�n�[�u�A�r�W�l�X���@�m�A���y�ʘ_���X�j���܂��܂ȕ���ɂ킽���Ă���܂��B
�@���U�w�K�̕��삩�猩��u���L�v�́A���̈ꕔ���ł��B
�@
�@���͕���12�N12���P���Ɂu���U�w�K�Q���C���X�g���N�^�[�i���U�w�K)�v�A����14�N�T���P���Ɂu���U�w�K�P���C���X�g���N�^�[�i���U�w�K�j�v�̎��i���u���L�v����݂Ŏ擾�������܂����B
�@����́u�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�̔F���S�āu���L�v����݂ł��������܂����B
�@�g�o�u���L���y�v��ҏW������Ɠ�l��g�ʼn^�c���A�܂����L�E�̐�y�����猴�e�̂����������Đ������Ă��܂����B
�@�����̑S�Ă̂��Ƃ����c�@�l�Љ�ʐM���狦��ɔF�߂��āu�܂Ȃт̒B�l�E�����т̒B�l�v�̔F�ւȂ��������̂Ǝv���܂��B
�@
�@
| �� 2005/03/01 (�sue)�@�n���ɂ����鑬�L�w���ɂ��ā@���̌�53�N�� |
�@�������L����@�֎��u���������L�v���a27�N�T���� ����35���ɂ����āA�u�n���ɂ����鑬�L�w���ɂ��āv�Љ�����܂����B
�@
�i�O���j
�@���܂ŁA�n���ɂ����Ă̎w���ɓ������āA�{���Ɏw���p�̏o�ŕ����o�Ă��邱�Ƃ�m�炸�ɁA��{�������v�����g������A�܂��͎w���҂��܂��܂��ȋ��ނ��쐬���A�z�t���Ă���Ƃ���������ɕ����y��ł���܂����A�����͖{���̏��F�Ȃ��ɂ���܂��ƁA���낢��Ȗ��╾�Q���N����܂��̂ŁA���̍ےn���̎w���҂͈ꉞ�{���ƘA��������Ă������������Ǝv���܂��B
�i�㗪�j
�@
�@�������L����쌧�x�����s�́u���������L�@�����v�̏㊪�͏��a26�N11���ł��B
�@���a26�N11�����珺�a27�N�T���A�܂�u���������L�@�����v�̏㊪�𒆍����L����{���֑������̂�12����{�Ɖ��肵�āA�u�n���ɂ����鑬�L�w���ɂ��āv�������ꂽ�̂͂R�����O��Ɛ����ł��܂��B�@�֎��̂T�������e���f�ڂ���Ȃ�Έ�����Ŋ����̑g�ŁA�ҏW�҂̍Z����ƂȂǂ��s���܂����班�Ȃ��Ƃ��P�����Ԃ͕K�v�ł��B
�@�P�y�[�W���e���f�ڂ��Ă���܂��̂ŁA�t�Z���Ă��R�����ɂ͌��e���ł��Ă����͂��ł��B
�@�u�n���ɂ����鑬�L�w���ɂ��āv�ŏ�����Ă�����e�Ɓu���������L�@�����v�㊪�́A�����I�ɂ��������Ă���܂��B�����̂܂������͏��a27�N�S��10���ɏ�����Ă���܂��B�����ł̏㊪�ɂ͂܂�����������܂���B
�@
�@���a27�N�T�����畽��17�N��53�N�Ԃ́A�e�n�ł��낢��Ȓ������̃e�L�X�g�ނ��쐬����Ă���܂��B
�@���T�C�g�́u�������W�����v�����Ă��������Ƃ��킩��̂悤�ɂ��낢��ȂƂ���Ńe�L�X�g���쐬����Ă���܂��B�������L����{���y�ђ��������L����{���ւ��f���𗧂Ăč쐬���Ă���܂���B
�@�قƂ�ǂ̒������W�҂͏��a27�N�T���́u�n���ɂ����鑬�L�w���ɂ��āv�͒m��܂��A�����w�Z�̑��L���A��w�̑��L������X�Ŏ��R�H�ɍ쐬���Ă���܂��B
�@�������L����{���Ō��O���ꂽ�悤�Ɂu���낢��Ȗ��╾�Q���N�������v�Ƃ͎v���܂���B
�@�S���e�n�ł͂��낢��Ȓ������̏��������ł��܂������A�g������̈����������͎��R��������Ă��܂����B
�@
�@
| �� 2005/02/25 (�eri)�@�E���ǂ݁@���������L�@���� |
�@�A�c�@�T�^��c�G�K���u���������L�@���� �㊪�^�����v���������L����쌧�x�����甭�s����Ă���܂��B
�@�㊪�͏��a26�N11���B�����ł͏��a27�N�S���R���A�����͏��a27�N�T���R���ɔ��s����܂����B
�@�u�����v�̂܂������ɂ́A
�@�������L����쌧�x�����A���̌`���Ȃ���Ȃ�ɂ��������̂́A�s�풼��̏��a20�N�ł������B
�@�����V�N�L�]���邢�͒��������搶�n�ɂ��}�����āA�e�����w�Z�ɑ��L�u�������肢���A���邢�͍��쌧�����w�Z���������L���Z���̊J�Âɋ��͂�������i�̎w���ɂ����͂�����Ă������ʁc�c
�i�����j
�@����ɂ�Ďx���ɊW�����l�X�̌����Ă����قǂ���N����Ă������Ƃ͓��R�̂��Ƃł���A���̂P�P�ɂ��ẮA�����������̉ߒ����o�āA�����悤�₭�A���̌��ʂ��܂Ƃ܂����悤�Ɏv����B
�@�K���A�����A�ۋT�����ƍ��Z���L�Ȃ̋����A���邢�͌�����ψ���̎�Â��鑬�L�u�K��ɋ@�āA�ȏ�̌����Ă��܂߂����쌧�x���ɂ�钆�������L�@�̑̌n�𗧂ĂĂ݂悤�Ǝv�����A����ɂƂ肩�������̂́A��N�i���a26�N�j�̂W�����߂ł������B
�@�����āg���������L�����h�Ƃ����������L����쌧�x���ŏ㊪���A�܂���N��11���Ɋ������ꂽ�B���������������܂Ƃߏグ�悤�Ɠw�߂����A�������̑��̊W�ňӂɔC�����A����ƍ����A�܂Ƃ܂�I������B
�i�����j
�@�]���āA���Ԃ�]�肩�����ɁA��A�����Ƃ��܂Ƃߏグ���̂ŏ��q�̓_�őa�R�̓_���������邱�Ƃ��A�܂����ɏグ���A����ɂ́A�����Ă��܂Ƃ߂��_�͒�������30�L�]�N�̗��j�ɔ�ׂāA���̎����o�����A�Ȃ��R�����A����Ɍ����̗]�n�������Ɏc����Ă���_�����\�ɓ������Ċ뜜������傫�ȓ_�ł���B���̈Ӗ��Œf���Ă��������̂́A���̂Q���Ɍf�ڂ��ꂽ�A���쌧�x���̌����ɂ�����ӏ��́A�{���̎��O�����Ă��炸�A�]���ĒP�Ȃ鍁�쌧�x���̂��̂������̂ł���A�ӔC�͑S�č��쌧�x���ɋA����Ƃ���ł���A�����͍���{���ْ̍�̌��ʂ��܂��āA���߂āA���̓���킯�ł���B
�i�㗪�j
�@
�@�u���������L�@�����v�̓��e�́A�]���̒������Ƃ͈قȂ��Ă���A�ȗ��@�����k�L�@�A���L�@�Ƃ����p����g�p���Ă���܂��B���������ȗ��̑傫�Ȍ������ʂ��Ǝv���܂��B
�@
�@�܂��������L����\���L��匤�����\�G���u�X�e�m�v�mo.�P�i���a32�N�W���S�����s�j�́u�ҏW��L�v�ɂ́A
�@�T���R���A���@�L�O���A������i�̒������L�w�Z�ŊJ���ꂽ�A�������L����̐V��������N�l��̐ȏ�A�V���ɐ�呬�L�����������邱�Ƃ����߂��A���̕ҏW�����쌧�x���ɖ�����ꂽ�B
�@
�Ə�����Ă���܂��B�������L����{������́A�ْ�̂������Ȃ������悤�ł��B
�@���ɂ͊��������i���������L�@�����j�������Ă���u�������̌��������Ă���낵���ł��傤���v�Ƌ���{���ւ��f���𗧂ĂĂ���悤�ɂ����܂��B
�@�����A�������L����{�����̒r�c����搶�́A�������L����ł͑����̎��͎҂ł����B���쌧�x���̂������]��ɂ����X�Ƃ������Ă���̂Ŋ��S���Ă���܂��B
�@�Q�l�܂łɁA�r�c����搶��48�A�A�c�T�搶�Ɛ�c�G�K�����24�ł����B
�@
�@
| �� 2005/02/21 (�lon)�@�E���ǂ݁@���{���L����E���� |
�@�������L����\���L�������\�X�e�m�mo.�P�ŁA���˔ɓy���u50�������Ɋւ�����_�v�ɂ��ď�����Ă���܂��B
�@���o���͂��Ă���܂��P�`16�ɕ�����Ă���܂��B
�@����13�̕�����
�i�O���j
�@����{�����̒r�c���ꎁ�́A��N��10��20���ɊJ���ꂽ���{���L�����Q��ψ���ŁA�ψ��̈���Ƃ��ē��������E��������ɓ�����
�@
�@����n���̕����ł����āA�����������̉��ς��s�����ɂ����Ȃ����̂������ā������Ɩ�����Ă�����̂����邪�A����͐��E��������̏ꍇ�A���ɗ��ӂ��đI�肷��悤�ɁB
�@
�Ƃ̈ӌ����q�ׂĂ���B�u�������̉��ρv�Ƃ́A�ǂ̒��x���w���̂ł��낤���B50�������̉��ς��܂߂Ă̂��Ƃ��낤���B�i�ꕔ�̈ӌ��Ƃ��āA50���������P�^�R�܂ł̉��ς͓�������Ƃ݂Ȃ��Ƃ����Ă���������ɋL������j�܂��A�������̉��ςɂ���ā������Ɩ�����Ă�����̂́A�V�����Ƃ��Ắ�������F�߂��A�ꎮ���𖼏��Ƃ����̂��A����Ƃ��������Ɩ���点�Ă͂������A���������E�����ɂ͂��Ȃ��悤�ɁA�Ƃ����̂��B���́���������������`�����i�҂����o���A�����Ƃ��o���Ƃ��Ă��c�c�B
�i�㗪�j
���`���i���݂̂P���j
�@
�@�u���{���L�N�\�v�ɂ́A
���a31�N10��20���@���{���L�����ψ���̑�Q���������ŊJ����A����E�����Ƃ���11���������肵�����A������͂�������F���Ȃ������B
�@
�Ə�����Ă���܂��B
�@
�@
�@