|
速記講座【15】 いろは歌
−−−−−−−−−−−−−−−−− この前は「イロハ」の順番と言いましたが、実はこれは仮名文字を1字残らず 使ってつくった1つの歌なんですね。漢字仮名交じりで書くとこうなります。 色は匂えど 散りぬるを 我が世誰ぞ 常ならむ 有為の奥山 今日越えて 浅き夢見し 酔ひもせず いろはにほへと ちりぬるを わかよたれそ つねならむ うゐのおくやま けふこえて あさきゆめみし ゑひもせす また、明治時代の黒岩涙香刊行の日刊新聞「万朝報(ヨロズチョウホウ)」− −「よろづ重宝」ともじったもので、スキャンダル記事中心に売り出し、それが いわゆる「三面記事」の語源ともなったとか。ここで明治36年(1903)に「いろは 歌」の替え歌を募集しましたが、そのときに一等をとったものはよく知られてい ます。 鳥啼く声す 夢さませ 見よ明けわたる 東を 空色映えて 沖つべに 帆舟群れゐぬ もやのうち とりなくこゑす ゆめさませ みよあけわたる ひんかしを そらいろはえて おきつへに ほふねむれゐぬ もやのうち (ゑ→え、ゐ→い) 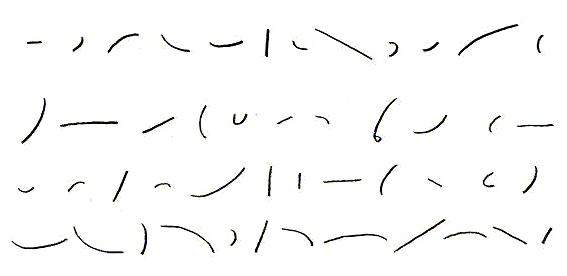
その後、昭和27年(1952)に「週刊朝日」が募集したときには 乙女花摘む 野辺見えて 我待ち居たる 夕風よ 鴬来けん 大空に 音色も優し 声ありぬ をとめはなつむ のへみえて われまちゐたる ゆふかせよ うくひすきけん おほそらに ねいろもやさし こゑありぬ 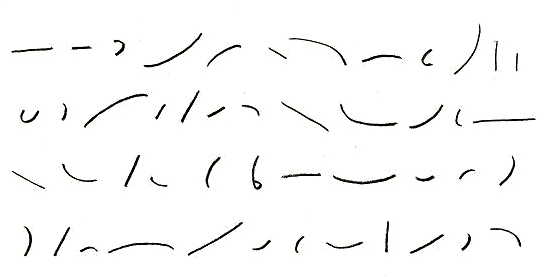
さらに、昭和43年(1968)、51年(1976)と「週刊読売」が二度にわたって募集し たことがあります。 たしか、ここの後期の方の入選作だったと思うんですが、 雪の故郷 お嫁入り 田舎畦道 馬連れて 藁屋根を抜け 田圃越え 葉末に白く 陽も添へむ ゆきのふるさと およめいり ゐなかあせみち うまつれて わらやねをぬけ たんほこえ はすゑにしろく ひもそへむ 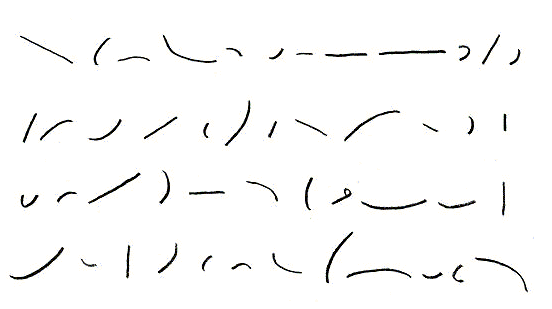
郷愁を誘うのどかな日本の情景を思い起こさせられ、速記の一線練習の材料に 使わせていただいております。なかなかのものですね。 しかし、何と言っても随一は、やはり「いろは歌」でしょうね。「ABC」な どのアルファベット−−ギリシャ文字のアルファとベータが語源だとか。この順 番に匹敵すると言われますが、そんな程度のものではありません。何しろ日本の ものは意味の込められた歌になっているんですからね。 作者は弘法大師(空海)だという説もありました。これはこの歌には諸行無常 の哲学的な意味が含まれているという解釈からだそうですが、国語学的にはア行 とヤ行の区別が失われてからの作だとされ、そうなると平安時代中期以降のもの ということになり、時代がずれてしまいます。 さらに、菅原道真の作だという説もあります。これは暗号を読み込んだという のです。7字ずつで行を変えて、その一番下の文字を読んでいくそうです。 いろはにほへと ちりぬるをわか よたれそつねな らむうゐのおく やまけふこゑて あさきゆめみし ゑひもせす 「とかなくてしす−−科(とが)なくて死す」となります。無実の罪で太宰府 に流され、失意のまま亡くなった菅原道真の怨念が込められているというわけで すが、これも俗説としか言いようがないですね。 道真の歌では、都を去るときに詠んだものがあります。天神さんと梅の由来の 1つですね。 東風吹かば 匂ひおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ |
